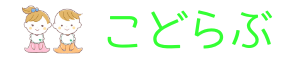赤ちゃんの笑顔と将来の病気や障がいの関連性について、ママやパパ向けにわかりやすくまとめています。
この記事で書いていること
- 赤ちゃんの笑顔と病気や障害の関連性があるのか
- 赤ちゃんがよく笑う理由と仕組み
- 本当に病気や障がいが心配なケースの例
- 赤ちゃんの笑顔の知識や笑わせるコツ
よく笑う自分の赤ちゃんって、やっぱりとってもかわいいですよね!
かくいう私も、生まれたばかりの息子の笑顔を「毎日ニコニコしていて可愛いな」と思って見ていたんです。
あるとき「赤ちゃんのときに笑いすぎていると将来自閉症などの病気や発達障害になりやすい」という記事を見かけて、ちょっと将来が不安になってしまいました…。
赤ちゃんの笑顔と将来の病気・障害の関連について調べてわかったのは、新生児や生後数ヶ月の赤ちゃんが笑いすぎだと感じても、将来の病気や障がいを心配しすぎる必要はないということです。
![]()
こんなママやパパにおすすめ
- 新生児や赤ちゃんが笑いすぎていて病気や障害の可能性が気になる
- 逆に赤ちゃんがあまり笑わなくて不安になるときがある
赤ちゃんが笑いすぎでも病気や障害になるとは限らない
新生児や小さな赤ちゃんが笑いすぎていることで、ママやパパが心配になるのは次のようなことです。
- うつなどの精神の病気
- 発達障害
- 自閉症
- 感情の異常
- その他の障害の可能性
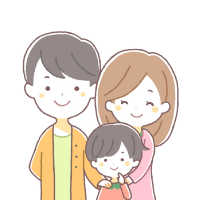
これを見たら「うちの子は笑いすぎだからすぐ病院に連れていったほうがいいかな…」なんて思うかもしれませんが、過剰な心配はしなくても大丈夫です。
なぜなら、赤ちゃんが笑いすぎていることと将来の病気・障害の直接的な因果関係を証明する確かな医学的根拠はないからです。
また、赤ちゃんが親の笑顔を見て笑い返すとき、赤ちゃんの脳内ではドーパミン(報酬系)が活性化することが研究で示されています。
これは、快感や喜びを感じ、記憶効率を高めることにつながります。笑顔が多いということは、親子の社会的交流が活発であり、五感が豊かに発達している証拠とも言えるため、むしろポジティブに捉えましょう。
赤ちゃんの笑顔の頻度と笑顔の仕組み
まず、赤ちゃんの笑顔について、以下の2つのことを覚えておきましょう。
- 赤ちゃんにも性格があるため笑ってくれる頻度に個人差がある
- 赤ちゃん特有の笑いの仕組みがある
それぞれをわかりやすく解説していきます。
赤ちゃんも性格があるため笑顔の頻度に差はある
赤ちゃんが笑うのは性格が明るいからというポジティブな見方もあります。赤ちゃんも大人と一緒で、一人ひとりにちゃんと性格があるんです。
たとえばですが、声を大きく出すのが好きな明るい赤ちゃんもいれば、あまり声を出したがらない赤ちゃんもいます。
いつも笑いすぎているからといって、なにか身体に異常を抱えていると断定する必要はありません。
赤ちゃんの笑顔の仕組み
実は新生児と生後数ヶ月以降の赤ちゃんでは、笑顔の仕組みは異なってきます。
新生児と、生後半年~1歳くらいの赤ちゃんの笑いの仕組みをそれぞれ解説していきましょう。
新生児の笑いは「新生児微笑」

新生児の笑いは「新生児微笑(生理的微笑・自発的微笑)」と呼ばれます。
新生児微笑は「反射」と呼ばれる反応で、主に赤ちゃんがREM睡眠中やウトウトしている時などに見られる笑顔に似た表情です。男の子・女の子どちらも共通で起こり、顔の表情筋の動きによるものです。
この微笑みは、単なる反射だけでなく、親の愛情を引き出し愛着形成を促すという、赤ちゃんが「愛されるための本能」として進化した重要な役割があるとも考えられています。
一生懸命に生きているので、体が勝手に反応してしまうということですね。
反射がいつまで起こるのかというと、新生児の時期を過ぎても、生後2ヶ月~6ヶ月の間は自然な反射が続くと産婦人科の先生も言っていました。ただし、生後2ヶ月頃から徐々に減っていきます。
新生児が笑うのは新生児微笑であり、反射や愛着形成のための本能が原因なので、この時期に笑顔が多くてもさほど心配はいりません。
生後数ヶ月~の赤ちゃんは「社会的微笑」

生後数ヶ月からの笑いは「社会的微笑」と呼ばれます。これは自分の意思により起こる笑いです。
生後数ヶ月以上経過すると、さらに赤ちゃんが笑いかけてくれる機会は増えます。
最初は人の顔を見て反応して笑うという感じですが、だんだんその回数は増えてきます。
- ふとママやパパと目があったとき
- 抱っこやおんぶをしてあやしてあげたとき
- ハイハイで追いかけっこをしたとき
- ボールやブロック・積み木などおもちゃで遊んでるとき
- 親子で一緒にお風呂に入ったとき
などなど、ニコニコしてくれるタイミングはたくさんありますが、さらに笑顔の機会が増えるのでとってもかわいいです。
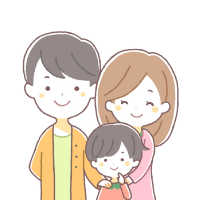
社会的微笑もまた、障害や病気と結びつくものではなく、感情が豊かである証拠といえるでしょう。
笑いすぎでも気にせず、どんどん親子間でコミュニケーションをとり笑わせてあげたほうが、感性がよくなり、むしろ成長にはプラスに働きます。
あまり笑わない赤ちゃんの方が危険かも
笑う赤ちゃんよりも、全く笑わない、もしくは笑顔が少ない赤ちゃんの方が心配が多いという意見が実は多くあります。
実際に自閉症や発達障がいなどを抱えた子どもの親御さんに話を聞いた結果、このようなことをいう親御さんがいたそうです。
- 「生後2ヶ月~10ヶ月くらいはずっと静かだった」
- 「おとなしかったのであまり手がかからなかった」
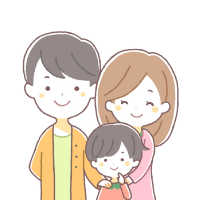
新生児のときなら笑わなくても心配はあまりないようなんですが、生後3~4ヶ月くらい経過しても全然笑わないという場合は、精神障害の心配もあるそうです。
医療機関での定期検査は皆様が受けると思いますが、心配であれば定期検査の時期じゃなくても、早めに医療機関に相談するほうがいいでしょう。
もちろん笑わない場合も多くの場合はあまり心配りません。表情やしぐさはよく観察してあげるといいでしょう。
-

1歳児はどれくらい言葉が喋れるのが普通?早い・遅いの判断目安
1歳児の言葉の発達について、目安などをわかりやすくまとめました! 1歳前後の子どもを子育て中のママやパパは、言葉の発達が気になる方もいると思います。 ママが心配になるケースは、大体は以下の2つのパター ...
続きを見る
よく笑う赤ちゃん=将来は賢く育つの?
よく笑う赤ちゃんは賢く育つという説もあります。
人が賢くなるにはシナプス=脳のつなぎ目を増やすことが必要になります。よく笑う赤ちゃんは脳が元気に活性化されるので、シナプスがたくさんできやすいんです。
シナプスは、幼児期が終わる6歳ごろまでが発達期間の目安なので、よく笑う赤ちゃんは賢く育つといわれているのです。
笑いすぎは心配かもしれませんが、笑顔には悪いことだけではなくポジティブな面もあるということも覚えておきましょう。
赤ちゃんの笑わせ方
無理に笑わせすぎるのもよくありませんが、赤ちゃんはかわいいですから、できるだけ笑ってほしいという欲求があると思います。
「あまり赤ちゃんが笑わないな…」というときには、ママやパパの方から笑わせてみるということも試してみてはいかがでしょうか。
ママやパパが、積極的に赤ちゃんや幼児期の子供とコミュニケーションをとることは、子育てには大切なことです。
たとえばですが、赤ちゃんを笑わせるためには次のような方法があります。
- たくさん笑顔で話しかけてあげたりハグをしてみる
- ちょっとだけこちょこちょしてみる
- 児童向けの音楽を聞かせてみる
- 公園にベビーカーで散歩に行ってみる
- 好きなおもちゃや教材などで遊んであげる
- 面白い絵本を読んであげる
- 高い高いをしてみる
- おいかけっこをしてみる
- 一緒に家族でお風呂に入ってみる
赤ちゃんの性格や好みにより笑ってくれるツボは全然違いますので、色々関わって試してみるといいでしょう。
愛情をもってスキンシップをし、深い関わりを持つことができれば、自然とニコニコ笑ってくれる回数は増えます。
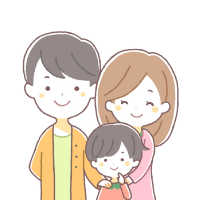
-
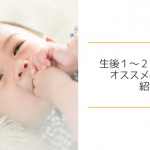
生後2ヶ月ごろの赤ちゃんの特長とオススメのふれあい遊び
生後2ヶ月ごろの赤ちゃんの発達の特長とオススメのふれあい遊びについて解説しています。 生まれて2ヶ月経過すると、新生児と呼ばれる時期をすぎます。さらに少しづつ成長しはじめる時期ですね! とてもかわいく ...
続きを見る
発達障害・グレーゾーンが気になる場合の対策は?
ここまで説明させていただいたように、多くの場合、赤ちゃんが笑いすぎでも発達障害を心配する必要はありません。
もし、それでも将来の発達障害や病気が心配という場合は、適応力を育てることを意識すると良いと言われています。
発達障害の子というのは、知能ではなく、以下のように適応力に遅れがあるケースが多いのです。
適応力に遅れのあるケース例
- 他の子よりちょっと感情表現が苦手
- 整理整頓ができない
- ちょっと言葉が遅い
発達障害には明確な白黒をつける定義がないため、このような発達障害と診断が降りる手前の状態はグレーゾーンと呼ばれています。
そんな発達障害・グレーゾーンの子たちが、発達遅れの対策のために使用している教材が天神という幼児教材です。
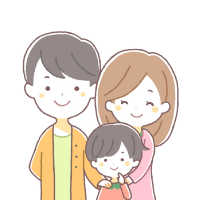
特に「笑わない」など発達に不安を感じる方は、お子様の個性や発達段階に合わせて、「適応力」を育むサポートを始めてみるのもオススメです。赤ちゃんから6歳まで利用できる天神は、発達の個人差が大きい時期だからこそ、親の不安に寄り添う教材として選ばれています。
気になる方は、まずは無料資料請求で、教材の内容と適応力育成の考え方をご確認ください。
![]()
赤ちゃんの笑顔と病気や障害の関連性のまとめ
まとめになりますが、赤ちゃんが笑いすぎだからといって心配する必要はあまりありません。
赤ちゃんが笑顔になるのにはちゃんと理由があり、笑わないよりはたくさん笑っている方が心配は少ないという専門家の見方も多いからです。
ただ逆に子供がほとんど笑わないという場合は、コミュニケーションの機会を増やしつつ注意してみる必要がありそうです。